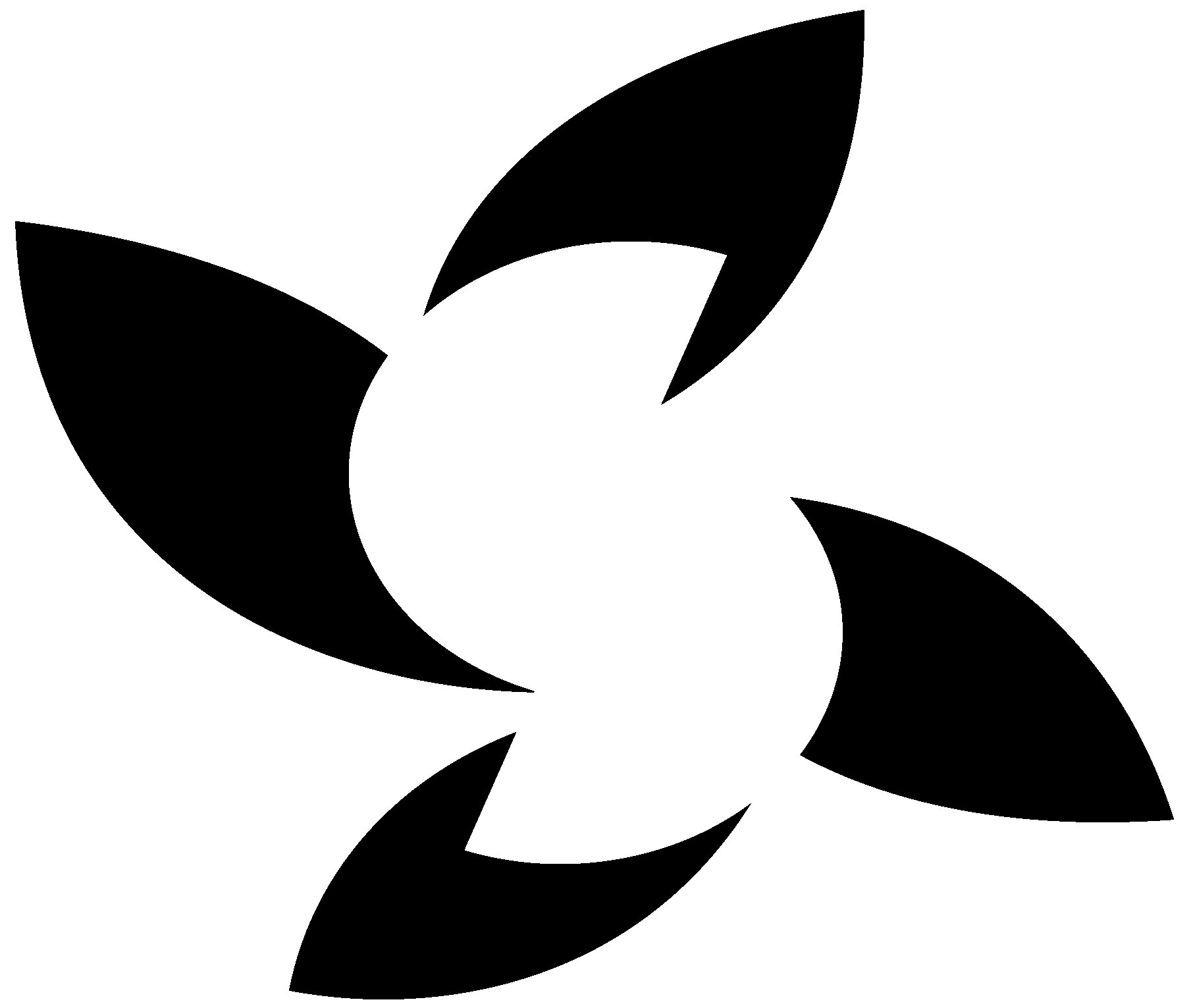プロセスセーフティマネジメント(PSM)の体系化と導入支援
SPSM研究会は、国際的に確立されたリスクベースのプロセス安全フレームワークを日本の産業現場に適用し、体系的な実装支援を行っています。
HAZOP・LOPA・SILなどの手法を統合するとともに、設備や操業管理を含む安全体制の定着を支援。さらに、IoTやAIを活用したスマート保安を取り入れることで、予知保全や継続的改善の仕組みを現場に根付かせています。

SPSMガイドラインと最新理論の実装
国内外の導入事例や研究成果をもとに、SPSM研究会は独自の「SPSMガイドライン」を策定。リスク低減策の妥当性評価、RBPS20要素の体系化を進めています。
これにより、国際理論を現場実務に展開可能な形に転換。さらに、サイバーリスク対策や情報セキュリティの最新理論も取り込み、デジタル化時代の安全マネジメントを支える枠組みを整備しています。

教育・人材育成と認定プログラム
2023年の法人化を契機に、教育プログラムと認定制度を拡充しました。基礎からスペシャリストに至るまで段階的に学べるカリキュラムを提供するほか、スマート保安や高圧ガス保安法の新認定事業者制度(A認定/B認定)対応プログラムも導入。
受講者は技術的知識だけでなく、制度適合や監査耐性を備えた専門性を習得できます。法人顧客にとっては、教育と認定が一体化した包括的な人材育成が可能になります。

産官学の研究連携
横浜国立大学先端科学高等研究院(IAS)を母体に、産業界や行政との共同研究を推進。エンジニアリング、法規制、マネジメント科学を横断し、スマート保安やリスク管理の新モデルを発信しています。
これにより、学術成果を迅速に現場へ展開し、実効性の高い安全対策を提供しています。

安全文化の定着と持続的改善
SPSM研究会は、単なる技術提供にとどまらず、組織全体の安全文化を醸成することを重視しています。監査や事故事例調査、マネジメントレビューを通じて、Continuous Improvement(継続的改善)を実現。
デジタル技術やスマート保安を組み合わせることで、現場に「リアルで実践的な保安力」を根付かせ、持続的に発揮できる体制を整えています。